どうも、ナカケンです。
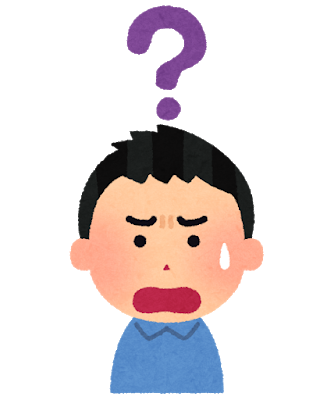
うまく溶接したいのに電気が合わないよ

ちょっとしたコツを掴めばそんなに難しくない!
いい溶接はいい条件から!
わかりやすく解説していくで!
ということで今回は
半自動溶接を行う際の電流、電圧調整のコツ
をお伝えしたいと思います。
溶接で最初にぶち当たる壁ではないでしょうか?
わかりやすく解説したいと思います。
ではいきましょう!
電流、電圧は溶接条件の一つ
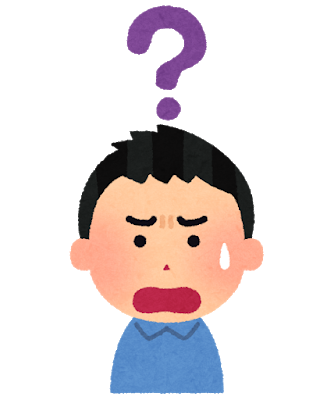
つーかそもそも溶接条件って何?

実際に溶接をする時の条件の事だよ。(そのまんま)何点かあげてみるよ!
- 母材の材質(軟鋼かSUSか等)
- 板厚(板の厚さ)
- 継手形状(突き合わせか、すみ肉か等)
- 開先形状(開先角度や、ルートギャップの有無等)
- 溶接材料(ソリッドワイヤーかフラックス入ワイヤか等)
- 溶接姿勢(下向きか、上向きか等)
- 溶接パラメータ(電流、電圧、速度等)
などがあげられますが、電流、電圧はその中の一つなんですね。
で、主に板厚や溶接姿勢で適切な電流、電圧は変化します。
板厚が厚ければ高くなりますし、薄ければ低くなります。
また、下向きでは高くなりますし、それ以外の上向きや、立向きの姿勢では低くなります。

ある程度幅はあるけど、低すぎても高すぎてもダメなんですよ。
例えば、すみ肉溶接で電流300Aで脚長6で上進溶接をやれって言われても多分無理です。
ビードが垂れまくって悲惨なことになるはず。
※この条件なら電流は180A-24Vくらいかな。

いい溶接を行うためには適切な電流、電圧に調整することが必然になるわけです。
業界では電気を合わせるなどと言います。
適切な電流、電圧に調整する=電気を合わせる

うまくできない人は先輩や親分にチェックしてもらいましょう。
電気が合ってない状態で溶接しても絶対にうまくならないよ!

まずは適切な電気の感覚を眼、耳、身体に覚えこませましょう。
とにかくいい電気で溶接すること!
今の溶接機はデジタル化が進んでいるため本体の表示を見るだけでおおよその確認はできますが、まだまだアナログのサイリスタ式の溶接機も現役でバリバリ活躍しています。

デジタルの溶接機じゃないと溶接できないよー。
なんて言えませんからね。

もちろん、フルデジタルの方がスパッタも少ないし、ワイヤの送給も安定してるけどね!

電気の合わせ方

さー、実際に電気を合わせていくで!
まずは電流から決めるで!
電流を決める

まずは電流から決めましょう。

溶接電流なんてどうやって決めるんですか?
これは先程も述べた通り、様々な要素が絡んできます。
私が普段溶接する中厚板(9〜22ミリ)くらいであれば、下向きで200〜260くらいでしょうか。

ほんとアバウトやな。何の参考にもならんわ

まーまー、そう言わんと!
開先を埋める場合もあれば開先無しの突き合わせ溶接もある。
ほんと、その時の施工条件で全然変わってくるで!
個人のスピードでも変わってくる。
一例を表にしたから参考にしてくれ!
| フラックス入りワイヤの場合 DW-Z100,SF-1等(全姿勢用) | |||
| 中厚板 | 突き合わせ開先無し | 突き合わせ開先あり | 隅肉脚長6 |
| 下向き | 180±20 | 250±20 | 250±20 |
| 立向き | 150±20(ショートアークで切りながら) | 200±20 | 180±20 |
| 横向き | 150±20 | 220±20 | なし |
| 上向き | 150±20 | 220±20 | 220±20 |

ざっとこんな感じや!あくまで一例やからこれより電気を上げる時もあれば、下げる時もある!
慣れてくれば高めの電気でも、手が追いつくんやけど、初心者の頃は手を早く動かすのがきついかもしれん。
少し電気を下げて丁寧にやるべし!
納期に追われている仕事の早い電気屋さんは大体電気が高いです。
上げりゃいいってもんじゃないですけどね。
電流=ワイヤの送給速度なので、電気を上げれば溶接は早くなります。
ここでおさらい
- 施工条件に合わせて電流は決める
- 初めのうちはやや低めで
- 慣れてきたら電気をあげる
- 電流=ワイヤの送給速度なので電気をあげれば溶接は早くなる
- あげればいいってもんではない、入熱が過大になるなど悪影響もある
- 常識の範囲内で自分に合った電流で溶接すること
溶材メーカーのカタログにも参考の数値は乗ってるのでそちらを参考にするのもいいですね!
電圧を合わせる

次に、電圧を調整します。
先に電流を決めてしまっているのであとはいい電気になるよう電圧を微調整していきましょう。
結論からいうと
電圧は機械任せでOK!
電圧調整については、ほぼ全ての機種で一元化の機能がついてるので機械任せでほぼOKです。
一元化、個別設定の違いはこちら。
しかし、自分で判断できる眼は養う必要があります。

いくら機械任せと言えども自分の目で判断できるようにはならんといかん
- スパッタ少ない。
- ビード形状適切
- 溶け込み適正
電圧が高い場合、低い場合をまとめるとこうなる
| 電圧 | |
| 高い | 大粒のスパッタが出やすい ワイヤが浮く感じでパタパタ音がする ビードは凹み気味になる |
| 低い | ワイヤが突っ込む感じでパンパン弾く ビードが凸気味 溶け込みは深い |
まとめ
長々と説明してきましたが結局皆さんにお伝えしたいのは
いい電気の感覚を体に覚え込ませること
これができないと、いつまでたってもうまく溶接できません。
いくら腕が良くても!です。
慣れるまでは先輩や親分に電気を見てもらうことを、おすすめします!
いい電気で溶接をする。

何より大事なことです!
電気みてくださいってお願いしても、

忙しいわ!そんくらいわかるやろ!ワシが若い頃は飯も食わんと練習しおったで!
なんて言われる環境じゃきっとうまくなれません。
うまくなるまでに時間もかかり非効率的。そんな職場はきっと生産性も低く給料も上がることはないでしょう。
こんな先輩や上司の下で働いていないかい?
この記事のような先輩や上司のもとで働いても時間の無駄!
見切りをつけるなら早いほうがいいと思う。
ではでは。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

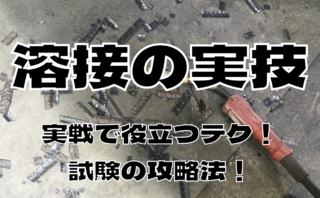
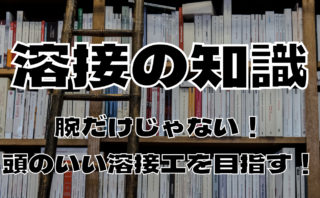

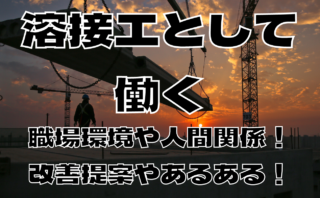
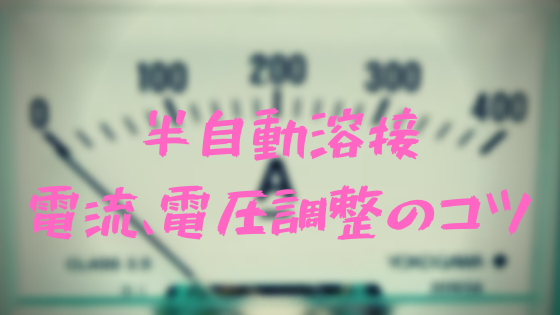
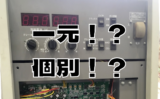



コメント